皆さん、こんにちは!
大家ふーしゅです。
今回は、

デッドクロスって何?
どういった状態のこと?
といった方向けの記事です。
不動産投資を始めてみようかなと思っている人も、既に投資家として活躍している人も、「デッドクロス」って言葉、聞いたことありますか?
ちょっと怖そうな響きですよね。
でも、心配しないでください!
今回はこの「デッドクロス」について、分かりやすく解説しちゃいます。
実はこれ、不動産投資・賃貸経営でけっこう重要なワードなんです。
知らないとちょっと損しちゃうかも!?
そんなわけで、今日はデッドクロスについてしっかり学んで、賢く投資を進めていきましょう!
それでは、さっそく始めていきますよー!
デッドクロスの基本
デッドクロスは、不動産投資でローンの元金返済額が減価償却費を上回ってしまう状態のことです。
つまり、支払いがあるものの経費として計上できない部分が多くなる状態を指します。
結果として、課税所得が上がってしまい、納税額が増えてしまいます。
デッドクロスの仕組み
不動産投資でローンを組むと、毎月返済を行いますよね。
その返済額は、元金と利息に分かれています。
利息の部分は経費として計上できますが、元金の部分は支払いは発生するものの、経費として計上できないんです。
一方、減価償却費は、支払いは発生しないけれど、経費として計上できるものです。
デッドクロスの状態では、ローンの元金返済額が減価償却費を上回るため、経費として計上できない部分が増え、納税額が増えるというわけです。
デッドクロスの状態
デッドクロスが続くと、課税所得が増えて手元に残るキャッシュフローが減ってしまいます。
場合によっては、納税額が手元のお金を超えてしまうこともあり、キャッシュフローがマイナスになる可能性もあります。
これは、不動産投資家としては避けたい状況ですよね。
デッドクロスのリスク
デッドクロスのリスクは、キャッシュフローが厳しくなるだけではありません。
納税額が増えて手元のお金が不足すると、ローンの返済にも支障が出る可能性があります。
これが続くと、不動産の維持管理も難しくなり、最終的には物件の価値も下がってしまう恐れがあります。
デッドクロスの発生原因
さて、デッドクロスがなぜ発生するのかについて話していきましょう。
デッドクロスの典型的なシナリオとして、築年数の古い物件や利回りの低い物件が挙げられます。
築年数の古い物件の場合
築年数の古い物件だと、減価償却費が高く設定されることがあります。
たとえば、築30年の木造アパートを購入した場合、減価償却費が4年間は高く計上されるんです。
しかし、5年目以降は減価償却がゼロになるため、課税所得が一気に増えてしまい、結果として納税額も増加してしまいます。
この結果、キャッシュフローが減ってしまい、デッドクロスが発生します。
利回りの低い物件の場合
利回りの低い物件の場合は、家賃収入に対してローン返済額が高いので、そもそもキャッシュフローが少ない傾向にあります。
このような物件でデッドクロスが発生すると、手元に残るお金がさらに少なくなり、最悪の場合はキャッシュフローがマイナスになることも。
経費計上の仕組みと元金返済の影響
デッドクロスの原因のひとつは、経費計上の仕組みにあります。
ローン返済には、元金と利息の部分があります。利息は経費として計上できるのですが、元金の部分は経費として計上できません。
また、減価償却費は、建物の価値が年々下がることを表すために計上される経費です。
この減価償却費は、支払いが発生しないものの経費として計上できるんです。
しかし、減価償却費が減っていく一方で元金返済額が増えていくと、経費として計上できない部分が増えていきます。
その結果、課税所得が増えて納税額が増加し、キャッシュフローが減少するというわけです。
デッドクロスの対策
デッドクロスは不動産投資家にとって厄介な問題ですが、幸いなことに対策があります。
今回は、デッドクロスを避けるためのいくつかの有効な対策を見ていきましょう。
1. 頭金を多めに入れる
まず、物件を購入するときに頭金を多めに入れると、ローンの返済額が減り、キャッシュフローが安定します。
少しでも頭金を多く入れられれば、ローンの元金返済額も減るのでデッドクロスのリスクを下げられます。
2. 借り換えによる金利や期間の調整
次に、借り換えを利用して金利や返済期間を調整する方法も有効です。
金利が低くなれば当然返済額も減りますし、返済期間を長くすることで月々の返済額も抑えられます。
3. 繰り上げ返済の活用
繰り上げ返済も対策として有効です。
繰り上げ返済をすると、元金の返済が減り、デッドクロスのリスクを減らせます。
ただ、手元の資金がなくなるのは避けたいので、余裕がある場合に限りおすすめです。
4. 新たな物件購入によるキャッシュフローの調整
また、新しい物件を購入してキャッシュフローを調整するのも良い手です。
特に減価償却が大きく取れる物件を購入すると、経費として計上できる額が増えて節税効果があります。
5. 利回りが高い物件を購入する
利回りの高い物件を購入することで、キャッシュフローが増え、デッドクロスのリスクを抑えられます。
ただし、利回りが高い物件にはリスクも伴うので慎重に選びましょう。
6. 売却による資産の組み替え
最後に、デッドクロスが発生する前に物件を売却して、資産を組み替えるという方法もあります。
売却することでキャッシュフローを安定させたり、新たな投資チャンスを掴んだりすることができます。
これらの対策を組み合わせて、デッドクロスを上手に回避していきましょう!
具体例
それでは、デッドクロスの事例を具体的に見ていきましょう。
今回は、築30年の木造アパートと、築浅のワンルームマンションの2つの例で説明します。
以下に、築30年の木造アパートの場合の表を、デッドクロスがどこで発生しているのかをわかりやすく修正します。
築30年の木造アパートの場合
築年数の古い物件では、減価償却費が高く設定されることが多いです。
このケースでは、減価償却期間が4年間と短いため、その後デッドクロスが発生しやすくなります。
| 項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃収入 | 450万 | 450万 | 450万 | 450万 | 450万 |
| 運営費 | 67万 | 67万 | 67万 | 67万 | 67万 |
| ローン返済額 | 229万 | 229万 | 229万 | 229万 | 229万 |
| 減価償却費 | 250万 | 250万 | 250万 | 250万 | 0万 |
| 課税所得 | -96万 | -96万 | -96万 | -96万 | 154万 |
| 納税額(30%) | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 46万 |
| キャッシュフロー | 154万 | 154万 | 154万 | 154万 | 108万 |
| デッドクロス | ✓ |
この表では、5年目からデッドクロスが発生しています。
減価償却がなくなった5年目には、課税所得が増加し、納税額も増えているため、キャッシュフローが大幅に減少しています。
築浅のワンルームマンションの場合
築浅のワンルームマンションでは、家賃収入が少ない上に、ローン返済額が高く設定されることが多いです。
さらに、減価償却費が少ないため、デッドクロスが発生しやすくなります。
| 項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃収入 | 120万 | 120万 | 120万 | 120万 | 120万 |
| 運営費 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 | 24万 |
| ローン返済額 | 100万 | 100万 | 100万 | 100万 | 100万 |
| 減価償却費 | 36万 | 36万 | 36万 | 36万 | 36万 |
| 課税所得 | -4万 | -4万 | -4万 | -4万 | -4万 |
| 納税額(30%) | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
| キャッシュフロー | -4万 | -4万 | -4万 | -4万 | -4万 |
| デッドクロス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
この表の例では、元金返済額の100万円に対して、減価償却費が36万円しかないため、元金返済額が減価償却費を大きく上回っています。
減価償却費を計上しても、キャッシュフローがマイナスになってしまいます。
このように、ワンルームマンションのような低利回りの物件は、デッドクロスが起きやすいです。
とういうか、初年度からデッドクロスの状態が継続しています😅
おわりに
いかがでしたでしょうか?
デッドクロスについて理解が深まりましたか?
今回の記事では、不動産投資におけるデッドクロスの基本や、その対策についてお話ししました。
これが皆さんの不動産投資の参考になれば嬉しいです。
不動産投資は奥が深いですが、正しい知識を持って取り組めば、大きなリターンも期待できます。
引き続き、楽しみながら不動産投資・賃貸経営を進めていきましょう!

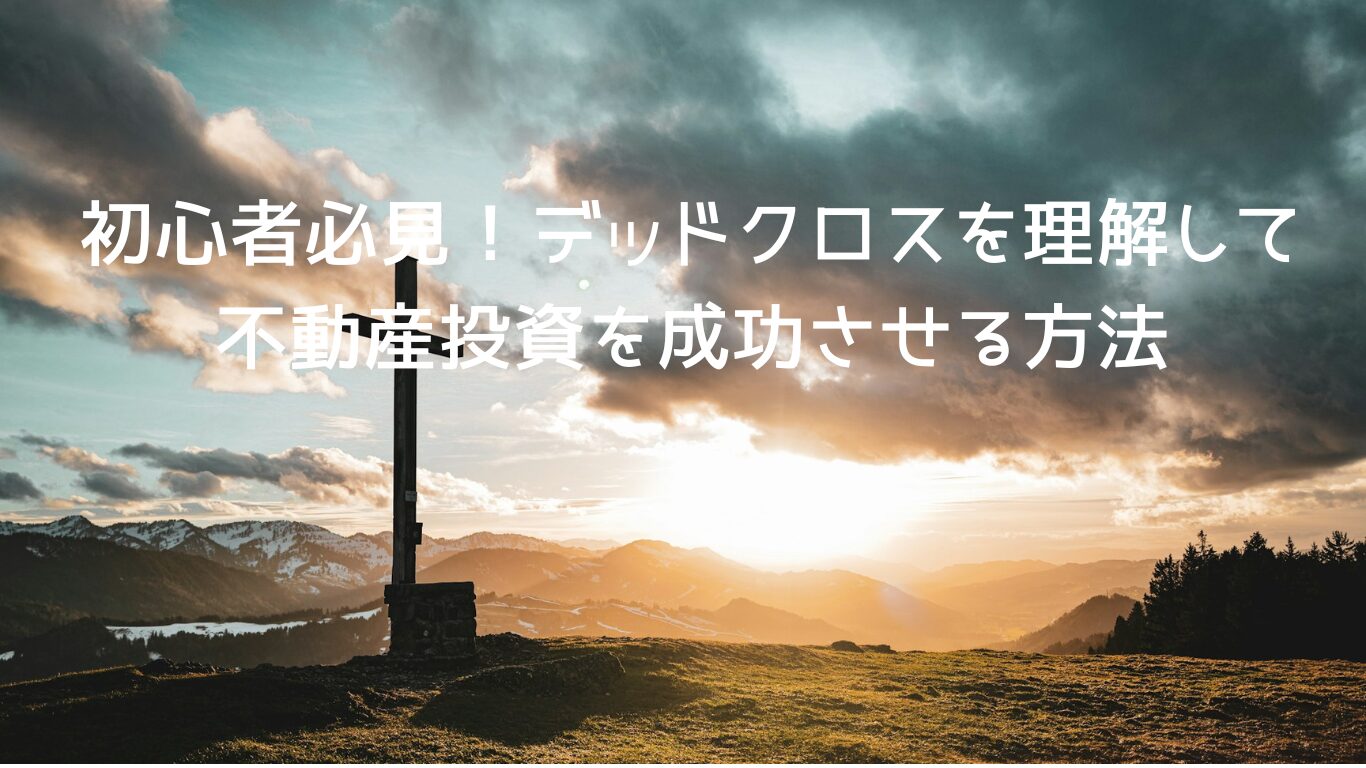


コメント