こんにちは。大家ふーしゅです。
賃貸経営をしていると、

生活保護の方や高齢者の方を受け入れても大丈夫かな…
って、どうしても不安になっちゃいますよね。
実際、リスクがゼロとは言えません。
滞納リスク、火災リスク、孤独死のリスク…。
ニュースで見聞きするたびに、心配になるのも無理はありません。
でも、きちんとリスクを理解して、
そのうえで対策をしっかり取れば、
生活保護受給者や高齢者の方を受け入れることは、
賃貸経営にとって大きな強みになることもあるんです。
しかも、これからの時代は高齢化がどんどん進んでいきます。
「高齢者OK」にすることで入居希望者の幅がぐんと広がり、
結果として稼働率アップにもつながるかもしれません。
この記事では、
生活保護や高齢者入居にまつわるリスクとその対策、
そして受け入れることで得られるメリットまで、
わかりやすくまとめていきますね。
「リスクを正しく知って、上手に付き合う」
そんな賃貸経営を一緒に考えていきましょう♪
生活保護受給者・高齢者の入居はなぜリスクと言われるのか?
生活保護受給者や高齢者の方の入居は、どうしてリスクが高いって言われがちなんでしょうか?
まずはその理由から整理してみますね。
賃料の支払い能力に不安がある
一番大きな理由はやっぱり、安定した収入があるかどうかです。
生活保護を受けている方の場合、収入源が行政からの支援になるので、
「本当に家賃がちゃんと払われるのかな?」って不安に思うオーナーさんは多いはず。
また、高齢者の方も、年金だけが頼りになっていたり、
急な医療費の出費で生活が厳しくなったりするケースもあります。
こうした背景から、支払いに対する心配はどうしてもつきまといますよね。
火災や孤独死、近隣トラブルのリスク
高齢者の方に関しては、
火の不始末による火災リスクや、
生活音をめぐる近隣トラブル、
そして何より孤独死といったリスクが考えられます。
特に孤独死は、
発見までに時間がかかるとお部屋の原状回復費用が高額になったり、
物件のイメージダウンにもつながってしまうので、
オーナーにとっては本当に気になるポイントですよね。
行政支援に依存する点への注意
生活保護受給者の場合は、行政から支援を受けている以上、
手続きの遅れや変更があったときに影響を受けることもあります。
たとえば、家賃支給のタイミングがズレたり、
制度変更で支給額が変わったりすることもゼロではないので、
こうした外部要因もリスクとされる理由のひとつです。
ここまで読むと、「やっぱり怖いかも…」と思うかもしれません。
でも大丈夫。
これらのリスクは、しっかり備えればコントロールできるものが多いんです😊
【生活保護】滞納リスクは代理受給でリスクヘッジできる
生活保護受給者の方を受け入れるとき、一番心配なのが
やっぱり「家賃、ちゃんと払ってもらえるのかな?」っていうことですよね。
でも実は、この心配、ある制度を使えばかなりリスクを減らすことができるんです。
家賃代理受給制度とは?
生活保護を受給している方は、本来は支給されたお金の中から家賃を支払うしくみになっています。
でも、中には家賃以外の出費を優先してしまったり、うっかり支払いを忘れてしまったりすることも…。
そこで活用できるのが、家賃代理受給制度です。
これは、行政が支給する生活保護費のうち、家賃相当額を直接オーナー(または管理会社)に振り込んでくれるしくみ。
つまり、入居者さんを経由しないので、
滞納リスクがグッと下がるんですね。
自治体によって制度の呼び方や手続きは少し違いますが、
「家賃分はちゃんと確保できる」という安心感はかなり大きいですよ。
生活扶助基準額が高いエリアはチャンスかも
さらに、意外と知られていないのが、
地域によって生活扶助基準額が違うっていうこと。
この基準額が高いエリアでは、
周辺の一般的な家賃相場よりも、
少し高めのお家賃で契約できるケースもあるんです。
たとえば、札幌市の場合。
単身世帯の住宅扶助(家賃分として支給される金額)は、
物件の広さにもよりますが、16㎡以上なら月額36,000円が上限になっています。
この金額よりも家賃が低い物件であれば、
相場より少し高めの家賃で入居してもらえる可能性もあるんです。
こう考えると、
「生活保護=家賃が安い」というイメージだけで敬遠しちゃうのは、ちょっともったいないかも。
エリアごとの扶助基準を調べてみると、
思わぬチャンスが見つかるかもしれませんよ♪
※住宅扶助の金額や適用条件は、年度や政策によって変更されることがあるので、
最新情報は札幌市の福祉事務所や公式サイトでチェックしておくと安心です。
参考資料:
生活保護受給者受け入れの注意点
もちろん、生活保護受給者の方を受け入れるにあたっては、
いくつか注意した方がいいポイントもあります。
このあたりをきちんと押さえておけば、
トラブルを未然に防ぎやすくなりますよ。
【高齢者】火災・孤独死リスクも対策次第で受け入れ可能
高齢者の方を受け入れるとなると、どうしても心配なのが
火災や孤独死といった、万が一のリスクですよね。
でも、これも対策をしっかりとれば、
グッと安心して受け入れられるようになります。
火災リスクには「IHコンロ」がおすすめ!
高齢者の方の火災リスク、特に注意したいのがガスコンロによる火の不始末。
記憶違いや体調不良で火を消し忘れ…なんてことがあると、本当に危ないですよね。
そんなときは、思い切ってIHコンロに取り替えるのがおすすめ!
IHなら火を使わないので、うっかり事故のリスクがグンと下がります。
しかも、最近のIHコンロはシンプルで使いやすいモデルも多いので、
高齢者の方でも安心して使ってもらえますよ♪
安否確認には「見守りサービス」も
孤独死のリスクについては、見守りサービスを取り入れるのが効果的です。
たとえば…
など、最近はいろいろな選択肢があるんです。
コストもそこまで高くないので、
お部屋の付加価値アップにもつながりますし、
何より、オーナー自身の安心感がぜんぜん違います。
もしもの備えに「孤独死対応保険」も検討しよう
どうしても、100%リスクをゼロにはできません。
そんなときに頼りになるのが、孤独死対応保険です。
この保険に入っておけば、
などをカバーしてもらえるので、金銭的なダメージを最小限に抑えることができます。
最近はオーナー向けの保険プランも充実してきているので、
もし不安が大きいなら、保険の活用も視野に入れてみるといいかもしれませんね。
このように、火災・孤独死リスクは「備え」でしっかりカバーできる時代です。
怖がるだけじゃなく、「どう備えるか」を考えていきましょう♪
高齢者を受け入れるメリット
高齢者の方を受け入れるって、リスクばかりが目立ちがちですが、
実はとっても大きなメリットもあるんです。
ここでは、オーナー目線で感じられる嬉しいポイントをご紹介しますね。
高齢者人口はこれからますます増えていく
日本はご存じのとおり、超高齢社会。
これからも高齢者の割合はどんどん増えていくと予想されています。
つまり、高齢者向けの賃貸需要は確実に伸びるということ!
今のうちから「高齢者歓迎」のスタンスを取っておくと、
将来的にも安定した入居者確保につながるかもしれません。
高齢者OKにするだけで間口が広がる
高齢者の方が入居しづらい物件って、実はまだまだ多いんです。
だからこそ、
高齢者の入居を受け入れるだけで、入居者募集の間口がぐっと広がるんですよね!
若い世代だけにターゲットを絞るより、
幅広い年代に対応できる物件のほうが、空室リスクも減らしやすいですよ。
社会貢献にもつながる
高齢者の住まい探しって、思った以上にハードルが高いもの。
だからこそ、受け入れ体制が整った物件は本当に貴重です。
オーナーとして高齢者の入居を受け入れることは、
社会的な意義もある素敵な選択肢。
「誰かの生活を支えている」
そんな小さな誇りを持てるのも、賃貸経営のやりがいのひとつですよね♪
このように、高齢者の方を受け入れることで得られるものは、
単なる「空室対策」以上に大きいんです。
築古物件こそ入居間口を広げるチャンス
築年数が経った物件を持っていると、

やっぱり新築や築浅には勝てないのかな…
なんて思っちゃうこと、ありませんか?
でも実は、築古物件だからこそ、チャンスがあるんです!
築古物件はターゲット拡大がカギ
どうしても築年数が経つと、
若い世代やファミリー層からの人気は落ちやすくなります。
そこで大事なのが、
入居ターゲットを広げるという考え方!
たとえば、
など、ターゲット層を少し広げてみると、
まだまだ安定した需要はあるんです。
実は「住み慣れた設備」が安心感につながることも
さらに、築古物件って、
高齢者の方にとってはかえって住み慣れた設備だったりすることも多いんです。
たとえば、
こういったポイントに、
「懐かしいなあ」「落ち着くなあ」って親しみを感じてくださる方も。
最新のオシャレな設備よりも、
素朴で使い慣れた空間を好む高齢者の方にとって、
築古物件はむしろ心地よい住まいになることもあるんです。
高齢者・生活保護受給者を受け入れるメリット
築古物件でも、
「高齢者歓迎」「生活保護受給者OK」
と打ち出すことで、競合物件との差別化ができます。
これによって、
といったメリットが期待できますよ♪
もちろん、受け入れる際にはリスクヘッジ策(家賃代理受給、見守りサービス導入など)をしっかりとっておくことが前提ですが、
築古物件でも収益力を落とさないための一つの戦略になるんです。
まとめ:リスクを恐れず、正しく対策して武器にしよう
生活保護受給者や高齢者の入居には、確かにリスクがあります。
滞納、火災、孤独死…、どれも無視できない心配事ですよね。
でも、きちんとリスクを理解して、
ひとつずつ対策を積み重ねていけば、怖がるだけじゃなく「強み」にも変えられるんです。
生活保護受給者には家賃代理受給制度を活用する
高齢者にはIHコンロ設置や見守りサービスを導入する
孤独死保険で万が一の備えもしておく
こんなふうに準備しておけば、
「入居者の間口を広げて稼働率アップ」も目指せるし、
「社会貢献」という、賃貸経営ならではのやりがいも感じられます。
築古物件をお持ちの方なら、特にこういった柔軟な視点が
これからの時代の強い武器になっていくはず。
リスクを恐れるよりも、
リスクを知って、上手に味方につける。
そんな賃貸経営を一緒に目指していきましょう。



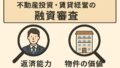

コメント